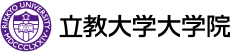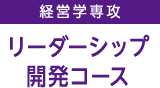中原淳教授は1年間の研究専念期間(サバティカル)を終え、2026年度4月より、立教大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース(LDC)に復帰する予定です。大学を離れてみたもの、考えたことはなんだったのか。研究専念期間(サバティカル)を半分ほど終えた中原教授にお話をお聞きしました。(インタビューは10月中旬に実施)

―研究専念期間(サバティカル)を、どのようにお過ごしですか?
中原 研究専念期間(サバティカル)を、海外の大学で学ぶ方や専門書の執筆に充てる方も多いのですが、私は「旅するサバティカル」というコンセプトで、1年間「ホーム」である東京と「アウェイ」である国内外の研究拠点、カンファレンスを行き来しながら越境学習することにしました。目的は2つ。自分自身のスキルアップや学び直しをすること。そして「アウェイ」で得たものを「ホーム」に持ち帰ることです。「ホーム」に何を持ち帰ることができるか、「越境学習」を意識して、4月以降、アメリカ、デンマークなど、海外の学会や研究機関を訪ねて回りました。
―海外を回られて、どのようなことに気づかれましたか?
中原 一番衝撃的だったのは、AIが労働力として捉えられていたことです。いまや「企業のワークフォース(労働力)」は「ヒューマンワークフォース(労働力としてのヒト)+AIワークフォース(会社全体の労働力)」なのであり、人事の役割は「人間とAIがどう役割分担をしていくか、ということを含めたワークフォースを設計すること」なのだ、というわけです。
最先端のカンファレンスでは「AIは道具ではなく、同僚であり知的パートナーである」ということも、当たり前のように語られていました。「AIが知的パートナーとなる」職場とは、どんな仕事をする時も「君のAIを連れてきて、二人でこの仕事をやってね」という世界観です。この視点に立つと、教育の設計も一変します。学習の単位が「人間一人」から「人間+AI」に変わるからです。例えば授業でSWOT分析を教えるなら、「分析のやり方」を伝えるだけでは足りません。プロンプトで問いを立て、AIと対話しながら思考を深めていく「AIと共に分析する方法」までも教える必要がある、というわけです。AIと共に働くことを前提に教育を考えていかなければならない、ということは、私自身にとっても大きなパラダイムシフトでした。
◇LDCを「AI前提の学び」のショウケースに
―現在、HR分野において、AIは主にどのような使われ方をしているのでしょうか?
中原 あらゆる領域で活用されていますが、最も進んでいるのは、採用領域ではないでしょうか。エントリーシートのスクリーニングはもちろん、学生が提出する動画のレーティングにも使っている企業もあります。動画から話している内容、緊張度合い、話し方、特性などを推定して、AIが一次選考の評価をするのです。最終的な判断は人が行うことが多いようですが、AIが偏った評価をしているケースはほとんど無く、採用や評価においてAIが人間より劣っていると一概には言えないように思います。こうした評価の補助だけでなく、離職アラートの通知、1on1の支援、配置転換のレコメンド、LMSでの学習提案、オンデマンド学習後の個別フィードバック…など、今、AIを使った機能はあらゆる領域で爆発的に増殖し続けています。このままいくと、「インターネット」同様、「AI」はあって当たり前の空気のような存在となっていくように思います。「インターネット」という言葉を若い人は使いません。インターネットは30年たって「死語」になりました。同様に「AI」も基盤技術として普及しになり、おそらくは「死語」になると思います。
―これからはあらゆる領域にAIが組み込まれ、仕事も学びもAIと共にあることが前提となっていく。社会の潮流が「AI前提」へと向かっている、というわけですね。
中原 その通りです。しかし、同時に目にしたのは、米国で経験の浅い若手の就職環境が急速に悪化し、リストラが激化している現実です。AIで代替可能な領域が広がる中、企業は「できるならAIで」「成果が出ない人は削る」とシビアに判断します。日本は人手不足やAI導入状況の違いもあり、多少の時間稼ぎはできるかもしれません。しかし、労働の現場がAI前提へと変わっていく以上、教育機関も変わらなければならない。このことは帰国後、強い危機感として私の中に残りました。
そこで帰国後、何人かの先生方にお声がけして、大学教育へのAI導入について検討をはじめ、まずは試験的にLDCコースに導入してみよう、ということになりました。といっても、全授業でAIの利用を強制するものではありません。AIを使うか使わないかは授業目的に従ってそれぞれの教員が判断すればいいと考えています。
―2025年9月からLDCでAIが導入されたのは、そうした経緯があったのですね。LDC生にはどのようなことを期待していますか?
中原 LDC生の中には、職場で日常的にAIを使っている方も少なくありません。ですので、ぜひその知見を共有していってほしいと願っています。実際、AIを導入した9月以降、「AI探究ラボ」というコミュニティを立ち上げ、LDC内で使い方やプロンプトの工夫を持ち寄る場づくりを始めました。私たちは生徒に挑戦を促しています。ならば、教員自身も挑戦しなければいけない。教職員とLDC生とで実践知を共有しあいながら教育実験をしていき、「AI前提の学び」のショウケースにしていけたら、と思っています。外に出る心配のないセキュアAIですので、どうぞ安心してジャブジャブ使ってください。
<参考>経営学研究科リーダーシップ開発コースの新たな取り組みについて-有償版生成AI(Google AI Pro for Education)の試験的導入-
―入学を検討している人の中には、AIを使ったことがない人、AIに苦手意識がある人もいるかと思います。そんな人でもLDCでやっていかれるでしょうか?
中原 「AIを導入」と聞くと、「ものすごく高度なことを求められるのではないか」と、不安になるかもしれませんが、AIが苦手でも全く心配ありません。教育機関の役割は、それを教えることだからです。プロンプトの作り方や効果的な使い方、ツールの選び方まで、基礎から学んでいきましょう。つまづいたとしても大丈夫。LDCは学びのコミュニティですから、そこには先輩や同期がいて必ず誰かが助けてくれます。2年間、AIを併走相手として使いながら、仕事の質とスピードを高めていくことに取り組んでいけば、修了時にはAIを賢く使いこなせるようになっているはずです。AIは使い方次第で、人を賢くする存在にもなることもあれば、人をバカにしてしまう存在にもなり得ます。みなさんにはぜひ、賢くAIを使えるようになっていただきたい、と思っています。
◇AIの奴隷にならないために必要な学びとは
―AIは「人を賢くする存在にもなることもあれば、人をバカにしてしまう存在にもなり得る」とは、どういうことでしょうか?
中原 AIは生産性をあげるけれど、人間の批判的思考力やメタ認知の能力を奪うという研究もでてきました。メタ認知的怠惰という状態といったりします。どんな道具も、使い方次第だと思います。最も危険なのは、AIに答えを求め、それを鵜呑みにすることです。自分の頭で考えるプロセスを手放すと、クリエイティビティも学力も落ちていき、AIの「奴隷」になってしまいます。人間は「思考停止した奴隷」になってはいけません。では、賢い使い方とは何か。私は「自分で考えて、自分で答えを出すことは手放さず、AIにフィードバックを求めて対話する」ことだと思っています。まず自分で仮説や分析を組み立てる。次にAIに問い、フィードバックを参考に確かめ、必要なら修正する。考える—尋ねる—確かめる—また考える、というAIとの対話を繰り返すことで、思考の質を高め、最後は自分で答えを出す、というのがAIの賢い使い方です。しかし、そもそも基礎的な知識が無ければ、AIと対話することも、自分で答えを出すこともできません。AIを賢く使うためには、これまでと変わらず、「基礎」をしっかりと学んでおく必要があります。
―これからはAIとの対話方法も積極的に学びつつ、自分で答えを出すためには、「基礎」をしっかりと学ぶ必要がある、というわけですね。「AI前提」の時代だからこそ学ぶべきことは他にもありますか?
中原 AIにできないこと、それは人と出会い、信頼を得て、情報を引き出し、考えるといった経験です。ここは、人が担うべき絶対領域です。今後、教育プログラムは、「科学知」と「臨床知」の二極へ向かっていくと考えています。AIやデータを使った高度な「科学知」を探究する一方で、チームビルディングや対話など、人と協働する実践を重ね、自分の身体を通して「臨床知」を探究する。大学は「科学知」と「臨床知」、この二極の極みに向かわないと、生き残っていけないのではないでしょうか。おそらく、一番代替されるのは「知識だけを一方向的に伝達する一斉講義」です。LDCは開講以来、理論と実践の往還、臨床知と科学知の融合、アカデミック・プラクティショナーの育成といった方針を掲げてきました。この方針をさらに極めていくことがAI時代の「勝ち筋」だと確信しています。わたしたちは「勝ち筋」を走りきります。
―「旅するサバティカル」、後半はどのように過ごされる予定ですか?
中原 臨床知の観点から人材開発・組織開発を捉え直す本を執筆しています。これまでと全く違う定性的な研究手法を使って、人の経験と語りを軸に実践知を記した本です。本の中では、10人にインタビューして、人材開発・組織開発の実践者がどのように今の仕事を形づくってきたのか、そのプロセスを追っています。10人の語りを通じて、実践の根源には若い頃の経験、子ども時代の出来事、あるいは前職で培った仕事の仕方など、個々の来歴が必ず影響していることが見えてきました。そうしたことに、それぞれの方が気づいていくプロセスを通して、最後は「人材開発・組織開発の仕事とは何か」を考える…という、かなり変わった本になりそうです。「旅するサバティカル」後半は、大阪大学で現象学の村上靖彦先生のゼミに参加させていただきつつ、この本を完成させる予定です。さらには、心ある協同研究者の皆さんと「人事異動の科学」と称した研究や、事業承継に関する書籍執筆も行っています。これらの成果がでてくるのではないか、と思います。
1年間の「旅するサバティカル」で越境学習した成果は、LDCにたっぷりと還元いたしますので、どうぞ楽しみにしていてください。LDCは、さらに「人と組織にまつわるプロフェッショナルたちが集うコミュニティ」に発展していきます。ぜひ、あなたも「わたしたちと同じ船」に乗ってみませんか? 2026年4月にお会いしましょう!
―楽しみにしています。ありがとうございました。