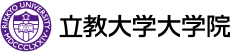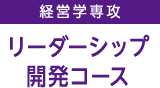企業の人事や人材開発に関わる仕事をしている人が多いLDCですが、医療に関わるお仕事をなさっている方もLDCで学んでいます。医療関係者がLDCで学ぶのはなぜでしょうか?2025年3月に修了された4期のお二人(那須さん・駒崎さん)に2年間の大学院生活を振り返っていただきました。第二弾は作業療法士の駒崎かんなさんにお話を伺います。
◇「人と組織について学びたい、という想いのある方は、臆することなく、そのままのパッションを持ってLDCにいらしてください」
LDC4期修了生 駒崎かんなさん(作業療法士・LDC事務局)

―駒崎さんは作業療法士ということですが、具体的にどのようなお仕事をなさっているのでしょうか?
駒崎さん 作業療法士とは、日常で必要となる「食事」「入浴」「更衣」といった日常生活動作能力や「料理」「買い物」「公共交通機関の利用」などの応用的動作能力、地域活動への参加や就学・就労といった社会的適応能力を維持・改善し、「その人らしい」生活の獲得を目的にリハビリテーションを行う専門職です。身体だけでなく、こころ(精神機能面)が重要で、うつ病や依存症、心に何かしら傷を負った方も含めて、その人がその人らしく生きていけるように日常生活のサポートするのが仕事です。もともと回復期リハビリテーション病院に3年勤め、その後地域のデイサービスに2年勤めた後、地域のデイサービスで非常勤として勤務を継続しながら、医療系の大学で作業療法学科の教員として学生の教育サポートを行う仕事をしていました。LDC修了後は、地域のデイサービスで作業療法士として働きつつ、LDC事務局の仕事をしています。
―なぜLDCで学ぼうと思われたのか、入学の理由を教えてください?
駒崎さん 作業療法士の仕事をやっていくなかで、病院組織やリハビリテーション組織の様々な問題に直面し、どう対処していけばいいのか悩んでいたときに、職場の上司がLDCを勧めてくれたのがきっかけです。作業療法士の仕事は単独では成り立ちません。患者様を取り巻くチーム内での多職種連携が重要なのですが、実際にはチーム内に権力構造があったり、職種ごとに方向性の違いがあったりして、なかなかうまく連携ができていないのが現状です。また、リハビリテーション科としての組織にも問題があることも少なくありません。これだけチーム医療・多職種連携が大事、コミュニティが大事、と叫ばれているにもかかわらず、なぜうまく機能しないのか、常々疑問に感じていたのですが、リハビリテーション業界で人材開発や組織開発に関することを専門的に学んでいる方は少なく 、個人が「勘と経験」で解決するには限界があると感じていたので、自分自身がより専門的に学び、人や組織に働きかける力を身につけたいと考え、受験・入学に至りました。
―実際にLDCで学んでみていかがでしたか?
駒崎さん 入学したその日からLWP(リーダーシップウェルカムプロジェクト)が始まり、異業種混合チームでのワークショップづくりが始まったわけですが、入学初日から医療人としてこれまで大切にしてきた価値観や思考が一気に崩れていく衝撃を受けました。医療業界ではアタリマエだった言葉や考え方がLDCでは全く通用しない。さらに、業界の異なる同期が使っている用語や発想にもついていけず、自分のことばがうまく伝わらないもどかしさもありました。医療業界しか経験をしてこなかった私にとって、これまでの自分を見直し、ゼロベースに立ち返る、まさに棚卸しが必要な状態だったと思います。特に入学直後の4月は、これまでの自分自身との対話や葛藤が続く日々で2年間の中でも苦しい時期でした。そんな中で大きな支えになったのが同期の存在です。一人ひとりのバックグラウンドは異なるものの、皆が温かい言葉をかけてくれたり、悩みに真摯に耳を傾けてくれたり、同じ目線で隣に寄り添ってくれる感覚がありました。その安心感と信頼関係があったからこそ、次第にLDCでの学びが楽しくなり、自分にとってのLDCや自身への意味づけが、少しずつ前向きなものへと変化していったのだと思います。また、LDCでは多くの授業で、振り返りの場が設けられており、自分自身と深く向き合い言語化する力を養うとともに、同期の振り返りを読むことで新たな視点・視野を得る機会が多くありました。こうしたLDCでの2年間の積み重ねが、振り返り・自己対話の習慣につながると同時に、自身の視座を高めることにもつながったと感じています。
―LDCで学ぶ中で、一般企業と医療の世界とで人や組織について、違いを感じたことはありますか?
駒崎さん 「中堅層の人材不足」や「入職1〜3年目の若手の早期離職傾向」などは、私がこれまで関わってきたリハビリテーション業界とも共通しており、大きく共感できる点でした。組織内における人材の定着や育成といったテーマは、業界を超えて広く共通する課題だと気づかされました。一方で、一般企業と医療現場では、組織構造や人材マネジメントの在り方に違いがあると感じました。また、那須さんと同様に、私も人事領域との接点がこれまでなく、LDCでの学びを通じて、初めて本格的に人事という領域に触れる機会を得たので、上記のような共通点・相違点に加えて、人事の方が果たしている役割の大きさや重要性に気づきました。
―医療をテーマにした唯一の授業、2年次の「医療とリーダーシップ」の授業はいかがでしたか?
駒崎さん 「医療とリーダーシップ」の授業が始まった時には、これまで1年次で学んできた理論や概念が、ようやく自分の実践とつながる手ごたえを感じました。なぜなら、自身の医療現場でのキャリア経験をもとに1年次に学んだことを再度言語化したり、医療現場における人材開発・組織開発・リーダーシップ開発についてのあり方を考えてみたりと、理論と実践を往還しながら学べる授業設計となっていたからです。医療系に特化した授業ということで、受講生は那須さんと私の2人だけだったこともあり、科目担当の保田江美先生とご相談のうえ、毎回対面形式で授業が行われました。少人数ならではの温かく濃密な学びの空間で、自分の考えをじっくり言語化でき、ディスカッションを深めることができました。毎回の授業が夢中になるほど充実していて、気づけばあっという間に時間が過ぎていったのを覚えています。特に印象的だったのは、最終回の授業にLDCの卒業生である医療系アラムナイの方々が参加してくださったことです。医療関係者同士が期を超えてつながる機会となり、視座がさらに広がりました。保田江美先生や先輩方との出会いをはじめ、多くの学びを得られたこの授業を受講できて、本当によかったと感じています。
―2年次のリーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)は、どのようなプロジェクトだったのか教えていただけますか?
駒崎さん LFPでは「急性期の総合リハビリテーション科における指導者によるコーチング行動促進に関する研究」をテーマに介入を行っていきました。クライアント組織の背景には、入社3年目以下の相次ぐ離職という組織の経営問題があったため、まずは課題を特定するために、インタビュー調査、フィードバックミーティングなどを複数回にわたって行っていきました。調査および現場の皆さまとの対話の結果、様々な課題が抽出されましたが、特にという点で、入社4年目以上の指導者における指導が一因として挙げられました。そこで、入社4年目以上の指導者におけるコーチング行動の促進を解くべき課題と設定し、入社4年目以上の指導者層を対象に2時間の介入施策を合計4回実施しました。また、介入施策実施後は、介入対象者である入社4年目の従業員と、指導者から日々指導を受けている入社1~3年目の従業員にインタビュー調査を実施しました。調査結果を分析した結果、指導者層の後輩指導における認知・行動変容と、現場でのコーチング行動の促進が確認され、入社1~3年目の従業員からも指導者層の行動変容が確認されたことから、介入における一定の効果はあったと推察しています。
―このような試みがリハビリテーション業界に広まっていくといいですね。最後に医療系の方でLDCを目指す方にメッセージをいただけたら、と思います。
駒崎さん LDCは、肩書きや業種・職種などの壁を取り除き、自分そのものを受け入れてくれる本当に温かな学びの場でした。入学当初は、医療人だからこそ強く根付いた価値観や考え方に自分自身が葛藤し、苦労することも多くありましたが、2年間の学びを通じて、自分の中にある医療人としての視点や経験こそが、LDCの学びをより深く、豊かなものにしてくれることに気づいていきました。また、バックグラウンドが異なる仲間たちとの出会い、互いの違いを尊重しながら学びを重ねていく中で、さまざまなバックグラウンドがあるからこそ共に創れる学びの力を強く実感しました。そのため、医療系の方で人と組織について学びたい、という想いのある方は、臆することなく、そのままのパッションを持ってLDCに飛び込んでみてください。そして同じ位パッションを持った仲間たちと共に学ぶ楽しさ、共に手を取り合ってゴールまで走りきる嬉しさを、ぜひ感じていただきたいです。私は今、LDC事務局のお仕事をしていますが、「医療とリーダーシップ」の授業をはじめ、医療系アラムナイ・医療系関係者として様々なところで接点が持てればと思っています!LDCでぜひお会いしましょう!皆さまとお会いできることを大変楽しみにしています!