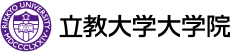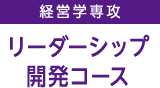企業の人事や人材開発に関わる仕事をしている人が多いLDCですが、医療に関わるお仕事をなさっている方もLDCで学んでいます。医療関係者がLDCで学ぶのはなぜでしょうか?2025年3月に修了された4期のお二人(那須さん・駒崎さん)に2年間の大学院生活を振り返っていただきました。第一弾は外科医の那須啓一さんにお話を伺います。
◇「我々のような別の領域の人間がスパイスのように混ざるからこそ貢献できることがあるし、得るものも必ずあります」
LDC4期修了生 那須啓一さん(外科医)

―那須さんは、医師ということですが、具体的にはどのようなお仕事をなさっているのでしょうか。
那須さん 前職の病院では外科内の数人の診療チームの責任者をやっていました。チームには常勤スタッフの医師の他に常に専攻医(外科専門医を目指す3−5年目の医師)や研修医(1−2年目の医師)が入っていて、3か月、短ければ1か月で彼ら彼女らは入れ替わるため、その都度、チームの雰囲気も変わります。また、手術や治療の際には他の診療科の医師や看護師、技師、ソーシャルワーカーなど多職種の連携が必要です。しかし、大都市の総合病院ともなるとどうしても組織が分断される「サイロ化」が進み、そのために連携がうまく行かないケースもあり、「このままで本当に患者さんのためになるのか?」という問題意識が常にありました。みんな「患者さんのために働きたい」と使命感を持って医療職に就いたはずなのに、現場ではその思いが十分に活かされていないのではないか。もっと患者さんの満足感を得つつ、そこで働く人たちが活き活きと働ける職場をつくれないだろうか…と書籍などを読み漁るうち、人材開発、組織開発という分野があることを知り、きちんと大学院で学びたいと、LDCの受験を決意しました。
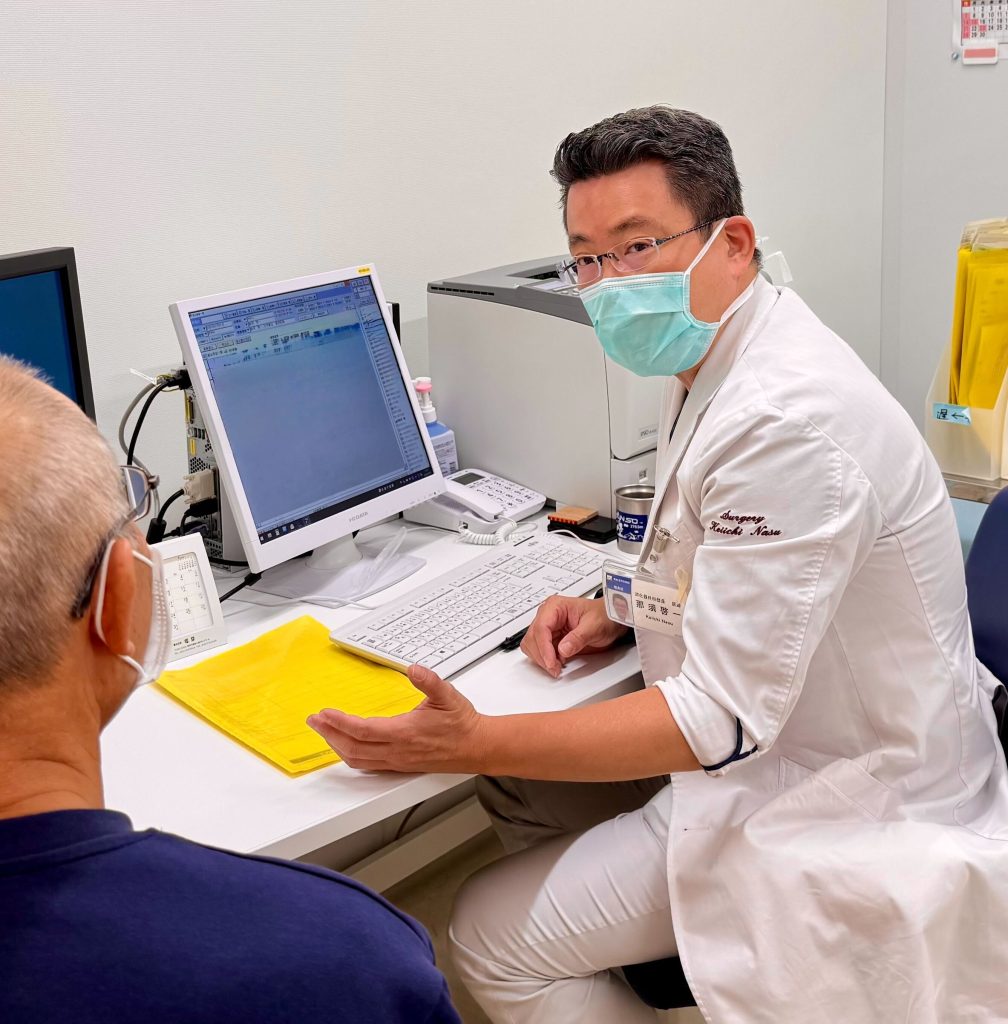
―専門化が進むことで、多くの職種の人が関わるようになって組織間に分断が起き、患者さんは一人なのに、上手く連携して機能させることが難しくなってきている、というわけですね。
那須さん それだけではありません。人手不足もあり、働き方改革などが進む中で、仕事と奉仕の感覚とをどう折り合いつけるのか、これから医師をどう採用し、どう育成するのか、といった問題もあります。自分自身も、チームを率いる管理職として、患者さんにとっては私のようなベテランが行った方が早いし確実だけれども、教育や今後のためには、研修医や専攻医といった修練中の医師にも信頼して任せなければならない…といったジレンマの中、バランスを取っていく難しさを感じていました。
―なるほど、組織の問題だけでなく、ご自身でもマネジメント課題を持っていらしたからこそ、LDCで人材開発、組織開発を学ぼうと思われたというわけですね。実際にLDCに入学していかがでしたか?
那須さん 正直、1年次のLWP(リーダーシップウェルカムプロジェクト)の時はしんどかったです。チームのメンバーが本当に優秀で、パワポづくりや資料まとめなどの事務処理能力も高くて。自分がチームに貢献できている実感が得られず、つらかったです。丁度仕事も忙しくなり、1年次はかなり無理をしてやっていて、このままでは仕事も大学院の勉強もどちらもダメになってしまう、と感じたので、2年次は無理し過ぎないよう、選択科目などは(全て受講したかったのですが泣く泣く)絞ることにしました。
―お仕事との両立は、どのようになさっていたのでしょうか?
那須さん もちろん、LDCを受験する前に、上司や当時の副院長などに相談し、授業のある金曜夜と土曜は勤務、当直やオンコール(緊急手術などの時に登院する役割)などは外してもらえるようにお願いしていました。ただ、グループワークなどで金曜、土曜以外にも時間が取られてしまうので、体力的に結構大変でしたね。2年次からは、LFP(リーダーシップ・ファイナル・プロジェクト)で自組織を対象とした研究、実践を行ったことで、周囲の病院のスタッフからも徐々に認知されるようになり、色々と気を使ってもらえて、ありがたかったです。
―LDCで学んでいるときに、一般企業と医療の世界とで人や組織について、なにか違いを感じたことはありますか?
那須さん そもそも、これまで人事の方にお会いしたことすら無かったので、人事のお仕事についての解像度はだいぶ高くなりました。そもそも、HRというのは我々の業界ではHeart Rate(心拍数)ですし、BPはBlood Pressure(血圧)ですので、HRBP(Human Resource Business Partner)と言われても、なんのことやらさっぱり分からなくて(笑)。しばらくは慣れなくて脳内で常に翻訳していました。
―全く違う世界に越境学習なさったような感じだったのですね。そうしたアウェイ感満載の中、医療をテーマにした唯一の授業が2年次の「医療とリーダーシップ」の授業だったわけですが、どのような授業だったのですか?
那須さん 「医療とリーダーシップ」は、1年間学んできた人づくり組織づくりに関わる知見を、現場にどう役立てることができるのか、どう実践につなげていくのかを探っていくような授業でした。実際に看護師としての経験もおありの担当の保田江美先生から医療現場での課題の抽出やその解決に向けて実践に繋げていった事例を知ることで、自分の職場にも活かせそうなイメージを持つことができ、これまでの授業で習った様々な抽象的な概念が現実の自分の職場に紐づけされていくような感覚がありました。LFPの相談にもとても親身に乗っていただけて、それもとてもありがたかったです。授業は論文を読んでディスカッションする、といったゼミ形式で行われました。私は医学部の時代もゼミ形式の授業はあまり経験していなったので、3人でじっくりディスカッションを深められたことも、とても良い思い出になっています。

―2年次のリーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)は、どのようなプロジェクトだったのか教えていただけますか?
那須さん 私は自組織の指導医としての課題をテーマとしました。私の病院は研修医から人気があり、優秀な医学生が当院での初期研修を希望して全国から集まってきます。しかし、臨床研修後、専門医資格取得を目指す専攻医として残る人が少なく他の病院や大学へ移動してしまう、という課題がありました。そこで、なぜ専攻医を目指そうとしないのか調査してみました。様々な理由があることが分かったのですが、理由の一つとして、専攻医として引き続き同じ病院でキャリアを重ねることに漠然とした不安がある、ということが分かりました。研修医のほとんどは医学生の時に専門科を決めているものですが、初期研修期間の2年間の中で進路に悩む人も少なくありません。そこで、4月に入職したばかりの1年目の研修医18名を対象に5年後、10年後のキャリアを考えたり、先輩の話を聞いたりしながら、自身のキャリアイメージを具体化していくようなワークショップを3回にわたって行いました。通常、医師に対してキャリア研修が行われるようなことは少なく、当院でも初めての試みだったのですが、2年目の先輩研修医や3年目の専攻医の方ほか病院関係者からの協力を得て実現しました。当院で専攻医としての専門研修を希望する医師が増えるかどうかは何年か経ってみないと分かりませんが、一定の効果は得られたように思います。
―臨床現場で研修に励む研修医の方々にとって、将来のキャリアを考える貴重な機会になったのではないでしょうか。最後に医療系の方でLDCを目指す方にメッセージをお願いします。
那須さん 医療関係者にとって、LDCで人材開発・組織開発を学ぶということは、かなりハードルが高いのは確かだと思います。ですが、LDCには多様性を尊重する風土が根付いています。教職員の方も同級生もそして先輩や後輩など期を超えて、みなさん本当に温かく受け入れてくださって、今思うと「むしろ壁をつくってしまっていたのは自分自身だったのかもしれない」という気がしています。最初の頃は特に「これだから医師はダメだ、とか、医療系だから解ってない、などと言われないようにしなければ」などと、自分で勝手に「医師代表」みたいな気持ちになって気負っていたのです。2年次の頃から、気負うことなく、自分の感覚で話をしても、「医療人ならではの視点」というのはしっかりと伝わるし、みんなの学びにつながり、自分の学びとしても返ってくるということを実感できるようになり、「思うままに発言しても、皆それほど気にしていないし、自分が感じた通りに自由に話してもいいんだ」と思えるようになってきました。今となっては、LDCでの学びの本質はそこにあったのだ、ということがよくわかります。こんな変わり種でも温かく受け入れてもらえたことが、本当に嬉しかったし、つくづくクラスメイトを初め学ぶ環境には恵まれたな、とみなさんには感謝しかありません。LDCには一般企業の人事や人材開発に携わる方が多いのは確かですが、その中に我々のような別の領域の人間がスパイスのように混ざるからこそ学びにおいて貢献できることがあると思うし、お互いに得るものも必ずあるので、入学を検討している人はぜひ挑戦してほしいです。次回「医療とリーダーシップ」の授業が開講した暁には、私は授業のサポートをしたいと思っています(保田先生もご了承済み!)ので、医療系の方、ぜひLDCでお会いしましょう。お待ちしています!