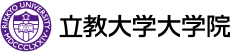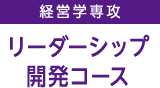2年次のリーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)は、2年間の集大成となるプロジェクトで、在学生それぞれが対象とするクライアント組織に対して、理論に基づき課題の状況をデータ分析し、経営・現場の視点で、人材開発・組織開発・リーダーシップ開発の取り組みを行います。
LFPは、約1年弱、クライアント組織と伴走しながら進めていくプロジェクトであるため、クライアント組織の方々のご協力が欠かせません。今回、立教大学大学院 経営学専攻 リーダーシップ開発コース(LDC)四期修了生である原田実咲さんと、原田さんのLFPのクライアント組織であるマルホ株式会社のご厚意により、初めてクライアント組織への取材が実現しました。
LFPはどのような形で進められ、クライアント組織にどのようなインパクトをもたらしたのでしょうか?LDCはクライアント組織の方々からはどう見えたのでしょうか?関係者の方々にお集りいただき、お話を伺いました。
マルホ株式会社 https://www.maruho.co.jp/
大阪府大阪市北区に本社を置き、医療用医薬品等の研究・開発・製造・販売を行う皮膚科学に特化した製薬会社。皮膚疾患治療薬(外用剤)の製造・販売で国内トップシェアを誇り、予防から治療、アフターケアまで、皮膚の悩み解決に向けた取り組みを進めている。
(取材にご協力いただいた方)
人事部長 後藤 礼子 様
人事部 人材開発グループ グループマネージャー 上杉 大輔 様(原田さんの前職での上司)
人事部 人材開発グループ マネージャー 山内 裕貴 様 (「1on1コミュニティ」の人事担当者。本プロジェクトでの主担当)
CMC企画部 テクニカルオペレーショングループ グループマネージャー 吉田 真一郎 様(「1on1コミュニティ」メンバー)
LDC四期 修了生 原田 実咲 様
(LFPのテーマ) 製薬会社の1on1における管理者フィードバック行動の促進に関するプロジェクト
LFPにご協力いただいた経緯
―原田さんは、なぜリーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)のクライアント組織をマルホ株式会社にお願いしたのですか?
原田さん(LDC四期修了生) 私は前職でメーカーの人事をやっていたので、LFPではメーカーの現場で活躍されている方々のお力になれるような研究がしたいと考えていました。マルホ人事部の上杉 大輔さんは前職の上司で、以前からいろいろ相談に乗っていただいていました。LDCで学んでいることもお話していたので、「クライアント組織になっていただけないでしょうか」とお願いしたのがそもそものきっかけです。
―上杉さんは、前職の部下である原田さんから最初にLFPについてお聞きになった時、どう思われましたか?
上杉さん(マルホ人事部) 最初に聞いた時は正直よくわからなかったです(笑)。研究のテーマは何なのか、その後何がどうなるのかもよく分からない。ですが、LDCの話は聞いていましたし、弊社の人材開発のメンバーにとって良い学びの機会になると考え、できる限りお引き受けしよう、と思っていました。
原田さん(LDC四期修了生) 一般的な大学、大学院の研究の場合、自分の研究テーマを持ったうえで、クライアントに「このような研究がしたいのでご協力ください」とご依頼するものかと思います。しかし、LDCでは経営戦略、事業戦略から紐解いていき、組織課題を特定させるところから研究をスタートさせます。そのため、どうしても「スケジュールは決まっていますが、テーマは決まっていません。人、組織の課題解決のお手伝いをします。お困りごとはなんですか?」などと漠然としたご依頼になってしまい…。最初は戸惑われたかと思います。
上杉さん(マルホ人事部) 戸惑いはありましたが、良い機会だと思ったのは確かです。弊社は人事部も含め、プロパー社員が多いこともあって一体感はあるのですが、少し内向きになりやすい傾向があります。事業を成長させていくために、社外の様々なパートナーと協業し新しいことに取り組んでいこう、という機運が高まっているなかで、LFPのようにアカデミックな研究プロジェクトに参画することは、人事としても学びにつながる良い機会だと考えました。また、全社的なプロジェクトではなく、対象者は少人数でもいい、といった話だったので、その位の規模感であれば対応できそうだ、と感じたのも、お引き受けした理由のひとつです。
事業環境とマネジメント課題
―LFPのお話を伺う前に、プロジェクトの背景となる御社の事業環境について簡単に教えてください。
後藤さん(マルホ人事部長) はい。弊社は皮膚科学領域に特化した製薬会社で、2025年に創業110周年を迎えました。直近10年間の成長率は約140%と右肩上がりで成長を続けています。2020年に社長が交代し、22年に経営理念(ミッション・バリュー)を刷新し、これまでの比較的トップダウンが強いマネジメントから、社員が各々の個性を発揮し、自律的に考え、ボトムアップで動けるようなマネジメントに変えていこう、という流れの中にあります。
―事業が順調に成長を続けている中で、マネジメント改革を進めているのはなぜでしょうか?
後藤さん(マルホ人事部長) これまで、右肩上がりで事業を伸ばし、多くの成功体験を重ねてきましたが、医療用医薬品をめぐる環境が大きく変化する中、今後はこれまでの勝ちパターンだけでは十分ではない、と考えているからです。製薬は研究開発に時間を要するということもあり、比較的長期の経営・事業戦略に基づく人材戦略が求められます。次の10年間に向けて、ハード面の体制整備だけではなく、自ら経験学習サイクルを回していけるよう、ソフト面でも変わる必要があり、そのために1on1など現場のマネジメントや上司の関わり方など、マネジメント変革のための施策が求められます。そうした中で、今回のLFPのように、実践を検証しセオリー化するアカデミックなアプローチを取り入れることは、内部での実践だけでは得られない示唆を得るまたとない機会になるものと考えています。
プロジェクトの概要
―原田さんのLFPテーマは「製薬会社の1on1における管理者フィードバック行動の促進に関するプロジェクト」とのことですが、プロジェクトはどのように進めていかれたのでしょうか。
原田さん(LDC四期修了生) はじめに行ったのは、解決すべき課題の特定です。外部・内部環境を分析し、マルホ様の人材戦略の背景には「事業ドメインの改革」があり、そのためにトップダウン型からボトムアップ型の組織への変革が必要で、自律的人材の育成を目指した1on1の導入はそのための施策のひとつである、と整理しました。しかしながら、1on1を推進していく中で、現場では思うように部下の行動変容につながっている実感が薄く、1on1の浸透を図れていない、というのがマルホ様からお聞きしたお悩みでした。
―1on1を導入したもののなかなか部下の行動変容につながらない…とはよく耳にするお悩みですね。プロジェクトの対象者はどのように選ばれたのでしょうか?
原田さん(LDC四期修了生) マルホ様では、有志の管理職の方々が「1on1コミュニティ」という1on1に関する勉強会を行っていました。この「1on1コミュニティ」の方々と共に1on1の質を高めていくことができれば、その成功事例を全社へ展開できると考え、今回のプロジェクトの対象者となっていただきました。プロジェクトを進めるにあたっては、「1on1コミュニティ」の方々と議論を重ね、自律人材についての定義を「業務に対する自律(革新的行動を行う)」とより明確にし、目指す姿を「1on1が部下育成の場と機能し、部下が自律人材になる(革新的行動を行う)」と再設定するところからスタートしました。
―山内さんは、人事部の主担当として原田さんのLFPをサポートしてくださいました。山内さんは1on1についての社内勉強会である「1on1コミュニティ」を担当なさっているとのことですが、コミュニティ立ち上げの経緯について教えてください。
山内さん(マルホ人事部) 2020年頃から、トップダウンでなく、一人ひとりが自律的に考え行動する力を伸ばしていくことを目指して全社で1on1施策を導入し、この数年、定期的にマネージャー・メンバー向けに研修を行ってきました。しかし、強制力を伴った施策としなかったこともあり、どうしても捉え方や推進・浸透度合いには差が出てきます。そこで、特に能動的、積極的に行っていただいている現場のマネージャーの方々にコミュニティという形で集まっていただき、1on1をレベルアップさせ、それを成功事例として全社に広めていくことを企図してメンバーを募り、1on1の社内勉強会「1on1コミュニティ」を立ち上げました。
―「1on1コミュニティ」とはどういった勉強会なのですか?
山内さん(マルホ人事部) 立ち上げメンバーは上記人事主催研修に参加いただいた管理職の皆さんの中から、継続的に自ら学びを続けたいと様々な部署から手を挙げていただいた有志の管理職7,8名です。現場でどうしたらうまく1on1を回せるようになるのか、どうしたら成果に繋げていけるのか、最初はお互いの悩み相談から始まりましたが、その後は傾聴、フィードバック、内省など各回にテーマを設けて、学術的な知見などを学びつつ、それぞれが持っている現場での実践をベースにディスカッションする、といったスタイルで月に1回ほど集まり、勉強会を続けてきました。
―現場で管理職をなさっている吉田さんはなぜ1on1コミュニティに参加なさったのですか?
吉田さん(「1on1コミュニティ」メンバー) 人事部による研修を受け、その通りに現場で1on1を導入してはみたものの、部下の行動変容につながっているといった、具体的な効果を実感することができずにいました。研修の中ではロールプレイなどもあったのですが、いざ現場でやってみると、きちんとできているのか自分ではよく分からず、果たしてこれでいいのかどうか知りたくて「1on1コミュニティ」に参加していました。今回のLFPのプロジェクトについても、自分の1on1を外部から客観的な視点で検証し、評価していただけるのではないか、という期待がありました。
原田さん(LDC四期修了生) 今回のLFPでは、コミュニティメンバーの管理職の方々だけでなく、その部下の方々にもたくさん定性・定量調査にご協力いただきました。調査の結果から、上司・部下間の関係性は良好ではあるものの、1on1によるコミュニケーションに部下はあまり意味を感じておらず、社員の自律促進にもつながっていない、ということが明らかになりました。これは、マルホ様に限ったことではなく、社員の自律促進を目的に1on1を導入したものの、実際にはコミュニケーション機会が増えただけ、という組織は少なくないように思います。
LFPにより浮かび上がった課題
―1on1についての社内調査結果については、どのように思われましたか?
吉田さん(「1on1コミュニティ」メンバー) 以前から傾聴の重要性は認識していたので、「1on1の際は、とにかく部下に話してもらって、しっかり聞かなければ」とばかり思っていました。ですが、調査により、部下の方はむしろ、上司からのフィードバックを求めていた、ということが分かりました。振り返って考えてみると、なるほど、と納得するところはありましたし、ある意味、弊社の組織文化みたいなところも関わっている課題かもしれない、といった気づきもありました。
後藤さん(マルホ人事部長) 今回の1on1に対する調査結果から導き出された課題は、ある意味でマルホのコミュニケーション全体に関わる課題でもあると考えています。ですが、それを人事が発信するのではなく、外部のコンサルが指摘するのでもなく、現場の管理職の方々と一緒に進めたプロジェクトを通して浮かび上がってきた、というのが何よりも説得力があります。
―調査結果を受け、どのような課題解決を行ったのですか?
原田さん(LDC四期修了生) 調査結果から、部下との関係性を大事に思うあまり、適切なフィードックを返すことができず、行動変容につながっていないような実態が見えてきました。コーチング施策が丁寧に行われていたことで「傾聴」はできていたものの、フィードバックに苦手意識を持っている人が多いことも分かりました。そこで、「1on1コミュニティ」の方々を対象に、フィードバックに関する知識を学び、スキルを身につけることを目的にした研修を、職場で実践していただきながら3回に渡って実施しました。
山内さん(マルホ人事部) 調査結果もさることながら、この課題をどのように解決していくか、というところにも、学術的な知見をベースにした様々なワークショップをしてくださり、本当に勉強させていただいて、ありがたかったです。
原田さん(LDC四期修了生) 山内さんには、裏側でたくさんご相談させていただきました。印象に残っているのは、1on1コミュニティのメンバーの方々と議論していた時に「誰がどんな行動をしていくと、この状況が良くなりますか?」と私が問いかけた場面です。山内さんが「部下にこうしてほしい、ということも分かりますが、私たちにももっとできることありますよね」といったことをおっしゃって、そこから流れが変わり「もっとフィードバックをやっていこう」と前向きな話になっていきました。
吉田さん(「1on1コミュニティ」メンバー) 我々「1on1コミュニティ」のメンバーも、それぞれが課題感を持っていて、これをなんとか自分たちで変えていきたい、そのために自分たちが動かなくてはならない、といった思いでこの活動をやってきました。ですので、原田さんと共に学びを深めながらこのプロジェクトを進めていくことができたのが、ほんとうに良かったです。
LFPを通じて起きた変化
―今回のLFPのプロジェクトを経て、ご自身の1on1についてなにか変化を感じる部分はおありですか?
吉田さん(「1on1コミュニティ」メンバー) はい。原田さんが、まずは「型」をしっかりと身につけることが大切だ、という話をなさっていて、実際に「型」を学んで1on1に臨んだところ、相手に対して自分がどう接しているのかを俯瞰的に捉えられるようになってきました。これまでに研修や書籍などを通して学んできたことも、「型」を意識することで実践につながりやすくなりましたし、自分の中で学びを上手く「実践できた、できなかった」という評価軸もできてきました。部下については、自分の学びを実践することで劇的に行動変容があった、ということはないのですが、以前よりも積極的に動く人が増えてきている気がしています。
―山内さんには今回、主担当として、原田さんと一緒にプロジェクトに取り組んでいただいたわけですが、いかがでしたか?
山内さん(マルホ人事部) 原田さんは、いきなり研修を行うのではなく、まずはしっかりと調査を行って課題を特定し、課題認識のずれを修正するところから始めて、科学知を入れつつ、しっかりとステップを踏みながら進めて下さいました。それがすごくありがたかったです。これまで人事として全社へのメッセージ発信・研修にて1on1の浸透を狙っていましたが、浸透には現場での「課題・悩み」にどのように1on1が応えられ、現場がどんな状態になり(何が実現でき)、そのために何を解決し、成果を出すことができるのか、の掘り下げが足りなかった部分が自身の中で改めて明らかになりました。今後予定している様々な人事施策をどう企画し展開していくのかを検討するうえでも、非常に有意義な気づきをいただいたと考えています。
―LFPプロジェクトが始まる前と後で、LFPに対する印象は変わりましたか?
山内さん(マルホ人事部) 最初は正直、学術と現場との距離感をどこまで縮められるのか不安がありました。科学知は非常に有意義である一方、それが実際の仕事にどう役立つのかを実感できないと、頭でっかちなやり方になってしまって実践に結びつかず、受け入れてもらえないことがあると、過去の経験から感じていたからです。ただ、我々がやりたいこと、なすべきことから始め、そこを学術的な知見で支えてもらう、というやり方で進めていただいたことで、メンバーの皆さんも「現場での成果につながっている」と実感しながら取り組むことができたように思います。このアプローチは私にとって大きな発見でした。
上杉さん(マルホ人事部) 私自身、アカデミックの知見と現場での実践が合わさるとすごく強いと思っているのですが、日々、現場で実務を回していると、どうしてもアカデミックな観点が欠けてきてしまいます。本来は忙しさを言い訳にせず、自分たちで学ばなくてはいけないとは思っているのですが、なかなか手が回りません。特に自分たちの取り組みがどうなのか、チェックを回していくようなことはこれまでできていなかったので、今回のような形でアカデミックな立場の方が加わってくださったのはとてもいい機会をいただいたと思っています。
吉田さん(「1on1コミュニティ」メンバー) 最初にお会いしたときは「テーマが決まっていない」とおっしゃるので、半信半疑…というより、不安しかなかったです(笑)。けれど、プロジェクトが進むにつれて、少しずつ違う景色が見えてきて、その積み重ねで大丈夫だな、という感じになりました。結果的に現場の課題から始めるというやり方でやっていただけたのがすごく良かったですね。現場の課題感を起点としたアプローチだったからこそ、解決策のところまでたどり着くことができました。個人的にはもう少し期間が長ければ、もっと効果が見えてきたのではないかと思っています。やはり人というのはそんなにすぐに変わらないものですから。
山内さん(マルホ人事部) 担当者としてはこのような調査や研究は、スポットで行われることがほとんどで、今回のようにほぼ9か月間、じっくりと伴走状態でやっていただいたのは初めてでしたし、その意味では期間もある程度まとめて実施いただいたことに意義を感じています。おかげさまで、こちらの悩みもずいぶん聞いていただき、細かいことも共有しながら進めていくことができたように思います。期間設定がある、というのもポイントで、1on1コミュニティのメンバーも含め、全員でしっかりと集中的に進めていくことができたのは「原田さんのLDC卒業がかかっている」という〆切効果も大きかったかもしれません(笑)。
原田さん(LDC四期修了生) そこはもう、みなさんお忙しい中、お時間を取っていただき、ご協力いただいたことが一番です。最後は論文の構成などについてもいろいろと相談に乗っていただいたりもしました。みなさまには本当にお世話になりまして、ありがとうございました。
―取材は終始和やかな雰囲気で行われ、LFPを通して、原田さんと担当者の方々との間に強い信頼関係が築かれていることを感じました。LFPというのは、単にLDC生が修了するために行う学術研究ではありません。クライアント組織の皆さまと共に行う課題解決であり、アカデミックで現場に成果をもたらす実践的な学術研究である、ということがよくわかるインタビューとなりました。原田さん、マルホのみなさま、ご協力いただき、ありがとうございました。

右からマルホ後藤 礼子 様、吉田 真一郎 様、山内 裕貴 様 、上杉 大輔 様、LDC四期修了生 原田 実咲様