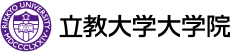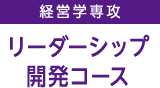LDC四期修了生 高松志直さん(片岡総合法律事務所 パートナー弁護士)
2025年3月に修了された四期の高松志直さんにLDCで学んだ2年間の大学院生活を振り返っていただきました。
―ご修了おめでとうございます。高松さんは金融関係の法務を専門とする弁護士とのことですが、なぜ人材開発、組織開発を勉強しようと思われたのですか?
高松さん(以下敬称略):理由は割とシンプルで、自分が所属する法律事務所の人と組織の問題をどうにかしたいと思ったからです。一緒に働いていた弁護士が辞めてしまったり、新卒から一緒にやってきた若手弁護士が辞めてしまったりしたことがきっかけで、7~8年前から自分なりに勉強を始め、様々な本を読み進めるうちに、人材開発、組織開発に出会いました。
―法律事務所に人事担当者はいなかったのでしょうか?
高松:勤務先の法律事務所は弁護士、事務職合わせて60名ほどの組織なのですが、実は人事部も無ければ、人事担当者もいません。そもそも私が知る限り、人事制度や人材育成システムが整備され、しっかりと機能している法律事務所は無いように思います。ですが、この領域のことを勉強すればするほど、人事や育成の仕組みが無いことに違和感を覚えるようになり、ついには弁護士の業務の傍ら、人事的なポジションを自主的にやるようになっていました。
―自ら人事担当者になって組織内の人と組織の問題をなんとかしよう、と思われたのですね。実際、離職する方も多かったのでしょうか?
高松:辞める人が特別多い、というわけではないのですが、新卒で採用し、何年も一緒にやってきた若手弁護士が、「そろそろ活躍してもらえるかな」というタイミングで辞めてしまう…といったことが続くと、やはりつらくて…。といっても、正義感から、ということではなく、辞めていくメンバーの話を聞く度にショックを受け、クヨクヨと考え続けてしまう自分が嫌で、「なにかできることはないか?」とこの領域の勉強をし始めた、というのが本当のところです。
―LDCに入学されたのはどういった経緯だったのですか?
高松:勉強をはじめて様々な人事関係の本を読み進めるうち、中原淳先生の「経営学習論」と田中聡先生の「経営人材育成論」に出会いました。両書籍とも非常に論理的に書かれていて分かりやすかったですし、なにより後書きや書籍全体からにじみ出る研究に対する熱量に感銘を受けました。周囲に人事の仕事をしている知り合いはおらず、中原先生にも田中先生にもお会いしたことはなかったのですが、このお二人がいらっしゃる大学院ならば、面白いかもしれないと思い、出願を決めました。
―実際に入学なさってみていかがでしたか?
高松:入学してみたら、企業で長年人事をなさっている人事のプロみたいな方も多くて、「やばいな」とちょっと焦りましたが、みなさん本当にいい方たちばかりだったので、ほっとしました。経営学の授業などもゼロからのスタートでしたが、事務所の経営にも携わっていましたので、全てが興味深く、楽しんで学ぶことができました。
―人材開発、組織開発の領域は、様々な研究知見やデータなどが蓄積されつつありますが、やはり“生身の人間のこと”なので、セオリー通りにはならない、一筋縄ではいかない難しさがあります。そのあたりの矛盾にはどう向き合われたのでしょうか。
高松:“生身の人間のこと”を扱うこの分野は、そんなに簡単なものではないだろうな、という感覚はありましたし、むしろそれを目の当たりにしたいと思っていました。法律を扱う弁護士という仕事をやってはいますが、もともと私は小説や漫画が好きで、言葉にならないような人間の複雑な部分に惹かれるところがありました。30代の10年は弁護士として論理モードでバリバリやってきましたが、いつもどこかにモヤモヤした感覚がありました。40代近くになって、コーチングを受けたり、人や組織について勉強したりするうち、自分がそうした“人間の生々しさ”に強く惹かれていることに気づき始めました。LDCでの2年間は、自分自身の中に、人に対する好奇心、チームや組織に対する関心が強くあることを確認し続けた時間だったように思います。
―LDCで学ぶことで、ご自身の中で確信に変わった、ということなのですね。印象に残っている授業などはありますか?
高松:リーダーシップ・ウェルカム・プロジェクト(LWP)のことを挙げる人が多いのですが、やはり私も挙げざるをえません(笑)。また、1年次からの秋学期のグループワークも印象的でした。全体的に、「こんなにもグループワークをやるんだ」と驚きましたが、1年間グループで振り返りを何度も何度も実践し、自分自身を深く見つめ直したことで、自己認知が深まりました。また、戦略と人事という文脈では、佐々木聡先生の「戦略的人的資源管理」、櫻井功先生の「戦略的人事実務論」の授業で学んだ内容は事務所の今後の人材育成の在り方を考えていくにあたって、非常に参考になりました。
―2年次のリーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)は、ご自身の勤務先の法律事務所を対象に行ったそうですね。どのようなプロジェクトだったのか教えていただけますか?
高松:テーマは弁護士の経験学習です。具体的には、事務所の若手弁護士に経験をリフレクションすることの意味を伝え、実践してもらいました。私の法律事務所においては、現状は、体系になっている中長期の人材育成プログラムのようなものはなく、基本的に現場でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を重視しています。ですので、しっかりと経験から学べるようにリフレクションを取り入れられたら、と考えました。
―育成プログラムが無い…というのは意外です。振り返りが苦手な若手弁護士の方が多かったのでしょうか?
高松:いいえ。実は、みんな振り返ることに抵抗感は無かったのですが、謙虚なタイプの人が多く、例えば、失敗ばかりを振り返ってしまう、という課題が見えてきました。ですので、今後は「成功したことからも学ぶことができる」という意識づけもできるとよいな、と思っています。取り組み自体から自分も多くのことを学べたので、今後は少しずつ対象者を広げていこうと考えています。また、上司との1on1ミーティングとのつながりも大切になるので、いずれは内省支援の研修などもやっていきたいです。
―高松さんは、LDCを修了し、今度は博士後期課程に進学されると伺いました。研究を続けようと思われたのはなぜですか?また、どのような研究を深めたいと思っていらっしゃるのでしょうか?
高松:深めたいと思っているのは今後の法律業務の在り方についてです。一般的に法律というのは形式ばった堅苦しいものだと思われていますが、実際には様々に解釈の余地を残しているものです。そのため、弁護士はただ法律の専門知識を持っているだけでは足りず、文脈や制度趣旨を適切に把握したうえで、法律を主体的に解釈することが求められます。しかも法律というものは全ての人に適用されるものですから、その解釈は多くの人に影響をもたらす可能性もあります。そのため、いかにして法的な議論としての論理を損なうことなく、併せて、様々な人の意図や想いといったものを取り込んだ解釈をするかが重要です。私としては、社会にとってより良い法律の解釈ができる弁護士が一人でも多く増えるよう、この領域の研究を進めたいと思っているんです。
―なるほど。そのためには、弁護士さんの人材育成にもっと力を入れていく必要がある、というわけですね。そのためにはどのような研究が必要だと思われますか?
高松:どの分野にもいわゆる“腕利きの弁護士さん”と言われる方がいらっしゃいます。そうした方々は、法律の専門知識が豊富であることは大前提なのですが、それだけではなく、法律の成り立ちの部分から理解したうえで事案に当てはめる力であったり、葛藤を乗り越える力であったり、様々な能力のバランスが取れているという感覚があります。まずはそういう方々はどんな能力を持っていて、どのようにしてその能力を獲得したのかを見ていきたいなと思っています。この部分が明らかになってくると、そのメカニズムを弁護士の育成に生かせるのではないかと考えています。一般論ですが、弁護士の中には、「間違いのないよう、ひたすら型通りに法律をあてはめるだけ…」という仕事が続くことで、やりがいを感じられず疲弊する人もいるかと思います。逆に、仕事を通じてしっかりと成長し、法律を主体的に解釈できるようになっていく実感を持つことができる枠組みがうまく業界で実装できれば、それぞれが弁護士としてやりたかった仕事に取り組むことができ、もっとやりがいを感じられるようになると考えています。そして、それは、法律業界の活性化につながり、きっと社会を良くすることにもつながるはずです。
―そのためには、LDCで人と組織について学ぶ弁護士さんが増えるといいですね。
高松:はい。2年間LDCで学んでみて思ったのは、必ずしも企業の人事に関わる仕事に就いている必要はなく、人や組織に強い関心があるのであれば、LDCへの進学を決めていい、ということです。ですので、弁護士だけでなく、他の士業や公務員の方々など、法律に携わるさまざまな方々にもぜひいらしていただきたいです。私自身、さらに研究を進め、将来は書籍を書くなど法律業界に貢献できるよう頑張りたいと思っています。