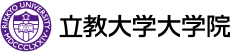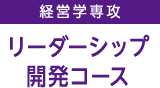リーダーシップ開発コース(LDC)では、学校の先生など教育関係の方も多く学んでいます。教育関係の方々がLDCで学ぶのはなぜなのでしょうか。LDCでの学びは教育現場で役立っているのでしょうか?教育関係のお仕事をなさっている1年次の柏木さん、木村さん、沖田さん、2年次の長谷川さんの在学生4名にお話を伺いました。
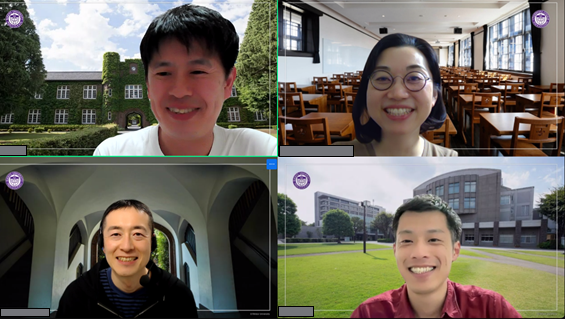
「学校現場にこそ組織開発が必要。先生方がワクワク働ける職場をつくっていきたい」
柏木さん(高校教員)
―柏木さんは高校の先生でいらっしゃるのですね。なぜLDCで学ぼうと思われたのですか?
柏木さん 公立高校の英語科の教員をしています。ただ、この4月からは教育委員会の制度を利用して学業に専念しています。LDCを知ったのはリーダーシップ教育がきっかけです。もともと、リーダーシップとは、できる人が発揮してみんなを引っ張っていくもの…というイメージがあり、自分とは全然関係ないものだと思っていました。ところが、ある時本を読んで、「全員発揮のリーダーシップ」という考え方を知り、「これなら私も発揮できるし、生徒たちもこれからの変化の激しい社会環境で必要なスキルなのではないか?」と感じたのです。当時私は「総合的な探究の時間」の担当者だったので、「探究」の時間にリーダーシップ教育を取り入れてみました。そうした取り組みをする中で、リーダーシップを生徒たちだけでなく、教員全員が発揮できるようになると学校が回りやすくなるのではないかな、と考えるようになったのが、LDCを志した1つめの理由です。
―そこで、LDCを受験なさったというわけですね。
柏木さん はい。ところが1年目は試験に落ちてしまったのです。2回目を受験するにあたっていろいろと勉強していくうち、学校という組織には「組織開発」が必要なのではないか、と思うようになりました。私は英語科の主任と研修の企画担当をしていたのですが、多忙で余裕がなく、研修に参加する時間を確保するのが困難な同僚もおりました。確かに業務量も多いのですが、個々で抱えこんでしまっているところを組織全体で業務を見直し整理すればもっとうまく回るのではないか、という気もしていて、学校現場にこそ組織開発が必要なのではないか、と。夏に中原先生が企画され、田中先生も参加されている電通育英会による「リーダー育英塾」に参加した際に、学校での組織開発事例を伺ったことで、その思いはさらに強くなりました。多忙感の強い今のままでは教員の採用倍率は低下する一方です。現場で出来ることは限られていますが、現場にいる自分たちでもできることがあるはずだ、という強い思いが2度目の受験を後押ししました。
―実際にLDCに入学し、学んでみていかがですか?
柏木さん 思っていた以上にグループワークが多いことに驚きましたね。私はこれまでも、いろんな形で チームで仕事することを経験してきたつもりなのですが、「チームとして働くとはどういうことか」を今、猛烈に考えています。昨今では教員の属人化、個業化ということが問題になっていますが、他ならぬ自分自身も当事者だったのだ、ということに今さらながら気づきました。本当の意味で「チームで働く」というのは簡単なことではありません。中原先生が「大人の学びは痛みが伴う」とおっしゃっていますが、自分自身と向き合い、これまで自分は同僚の先生方とどう接してきたのか、ということを“痛い”思いをしながら振り返る日々です。
―教育とは縁遠い経営学を学ぶというところに関してはいかがですか?
柏木さん 経営については、ハードルが高く、始めはついていくのに必死だったですが、人的資本経営や経営戦略について学ぶ授業で、自組織について考察する課題が出されることが多く、経営の視点で所属する組織について考えるようになりました。様々なフレームワーク等を用いて勤務先の高校の外部環境や内部環境を分析したり、ビジョンについて考えてみたりと、今まで持ったことの無かった視点で組織を捉えることで、新しい発見がたくさんあり、すごく面白かったです。実際、教員採用の対策を考えるうえでも大切なことです。とはいえ、学んだことを学校という組織で活かしていくためには、経営用語、ビジネスの言葉を教育現場の言葉に変換して伝えていく必要があるだろうな、ということも感じます。私は今年1年、職場から離れているので、復帰したら、職場はどう見えるだろう?自分はどう変化しているのだろう?と今からドキドキしています。
―入学希望者にメッセージをお願いします。
柏木さん 私は教員の仕事というのは楽しい仕事だし、すごくやりがいのある仕事だと思っているので、今、教員の仕事に対してネガティブなイメージを持たれてしまっていることをとても残念に思っています。先生方がワクワク働ける職場をつくっていきたい、という思いをお持ちでしたら、ぜひ私たちと一緒に人材開発、組織開発をやっていきましょう!教員の方にとってLDCは、単に知識を身につける場というだけではなく、視野を広げるという意味でも貴重な場かと思います。同期には、いろんな職種の人がいて、多様な考え方に触れることができます。グループワークで意見を交わすだけでも、「ああ、そんな風に考えるのだな」「そんな視点もあるのだな」と発見があり、めちゃくちゃ勉強になります。なによりお互いに学びあえる仲間がいる、ということは本当にありがたいな、と感じています。ですので、「迷ったら飛び込め!」とお伝えしたいです。
「先生たちにとって学校を魅力的な環境にしていく仕事をぜひ我々と一緒にやりませんか?」
長谷川さん(2年次・教育委員会勤務)
―長谷川さんは教育委員会にお勤めということですが、お仕事内容とLDCを志した理由を教えてください。
長谷川さん 島根県の教育委員会事務局に勤務し、教育委員会が掲げる「県立高校魅力化ビジョン」の進捗管理・打ち手の検討を進めるプロジェクトチームの事務局を担当しています。私は教員ではありませんが、いかに学校現場の先生方が生き生きと働き、生徒たちに全力で向き合える環境を創れるかということが、何より大切な役割だと思っています。教育委員会に来る前は5年ほど、福島県の県立高校に常駐し、先生方と一緒に学校づくりに携わっていました。その中で、教育の世界は、生徒たちが最優先なので、どうしても先生たち自身のことは二の次にされてしまいがちなところがあると感じました。生徒たち以上に、本当は先生たちも日常の中で学び、自らを高めていきたい。そうであるならば、先生たちにとっても学びに満ちた学校を創っていくことが、結果的に先生たちの力が存分に発揮されることに繋がり、より良い教育が生まれていくと思いました。いまはそんな学校をより広く創っていくために、教育委員会という立場で仕事をしていますが、先生たちにとってより良い学校や教育委員会の組織を創っていくという観点で、LDCで人材開発、組織開発について学び、公教育における組織づくりに役立てたい、と思うようになったのがLDCを志した理由です。
―以前からこの分野についてはご興味がおありだったのですか?
長谷川さん はい。以前から組織づくりには関心があり、個人的に経営学を学ぶ講座を受講したり、チームコーチングを学んだりもしていたのですが、知識や観点はやはり断片的なものであり、もう少し腰を据えて人材開発、組織開発を学び、その全体像をつかみたい、と考えたのも大学院を志望した理由の1つです。また、中原先生とは前職のNPO法人の理事をなさっていた関係でお話する機会があったのですが、その中で「定義されていない課題に向き合うことがあなたたちの仕事。世の中で光が当たっていない問題に光をあてて解決することが大事」と説く中原先生の言葉に影響を受け、教育委員会の人材開発、組織開発という、これまであまり世の中で触れられてこなかったテーマ、課題に向き合いたいと思えたのも大きいです。
―実際にLDCで学んでみていかがでしょうか?
長谷川さん 入ってみて一番意外だったのは「チーム活動が多い」ことです。大学院での学びは個人で研鑽を積む、というイメージがありましたが、LDCは想像以上にチーム活動が多くて驚きました。といっても、いい意味での驚きです。お互いにフィードバックしあったり、学び合ったりする中で、学びを深められるし、チームでやっていくとはどういうことか、ということを実践的に学んでいくことができ、単なる知識の獲得に留まらず、身体を全部使って学んでいく場所なのだと今では思っています。
―長谷川さんは現在、2年次でご自身の職場をクライアント組織としてリーダーシップ・ファイナル・プロジェクト(LFP)に取り組んでいらっしゃると伺いましたが、いかがですか?
長谷川さん LFP、とても充実して、楽しみながらやっていますね。教育委員会に来て、これだけ職場内部の人のことについて考えたのは初めてだと思いますし、それをプロジェクトの方々と一緒に議論することでたくさんの学びもあります。もちろん、研究の一環ではあるので、なかなか学術概念との繋がりが見えてこなかったり、論理的に報告書にまとめることが大変だったりと、しんどいこともあるので「たのしんどい」という感じですが(笑)。LDCに入学以来、この職場で人と組織の知見をどう活かせるだろうか、という問いに向き合い続けてきました。自分にできることをやってきた中で、今はLFPを通じて自組織に深く介入し、学んできたことを実践に活かしていく中で、いろいろと見えてきたものがあります。やはり理論的背景でまとめていくところは慣れていないので大変ですが、クライアントも関心を持ってくれているので、しんどいですが、良い示唆が得られるよう、頑張っているところです。
―入学希望者にメッセージをお願いします。
長谷川さん 生き生きと働く大人がいてこそ、魅力ある教育環境が実現していくと思っています。そこには、そんな大人を支えるより良い組織づくりが重要です。より良い組織づくりには、組織づくりの専門家が必要です。しかし、教育業界で人材開発、組織開発の領域に関心を持っている人は、まだまだそれほど多くありません。現状を変えていくためには仲間を増やしていくことが大切だと思っています。先生たちにとって学校を魅力的な環境にしていくという領域に関心を寄せてくれているのなら、ぜひ我々と一緒に学びを深めませんか?LDCで、そんな皆さんをお待ちしています!
「学校を幸せな場所に変えていくための鍵は人材開発、組織開発にある」
木村さん(1年次・高校教員)
―木村さんは、県立高校の先生でいらっしゃるということですが、なぜLDCで学ぼうと思われたのですか?
木村さん 青森の県立高校の国語科の教員をしています。LDC入学のきっかけは、いくつもあるのですが、まずは今の学校で普通科主任という十数人のチームを取りまとめるミドルリーダー的な立場になった、ということがあります。主任という肩書はついたものの、職場の人たちをどうやって伸ばしていけばいいのか?どうすればチームとしてまとめることができるのか?については、どうしたらいいのか見当もつかず、課題感を抱えていました。また、私は探究学習カリキュラムの作成、ICTの導入や先生方の研修などを担当する研究開発部の主任でもあるのですが、こちらの方にも課題を感じていました。勤務先の高校は探究学習に力を入れているので、先生方が探究学習に取り組めるように試行錯誤していたのですが、もっと先生たちを巻き込む方法はないだろうかと調べたり、様々な方のお話を聞いたりするうち、どうやら“経営学”の知見が役立ちそうだ、ということに気づきました。学校教育の世界ではよく「校長のリーダーシップが重要だ」などと言われますが、リーダーシップの定義を明確にしていないように感じられ、経営学とは縁遠い世界です。もし自分が経営学を学び、戦略やリーダーシップなど経営学の知見を学校に持ち込むことができたら、もっといい形で学校運営ができるのではないか?と考えるようになり、LDCの受験を決めました。
―4月から今まで、LDCで学んでみていかがですか?
木村さん 長谷川さんが「たのしんどい」とおっしゃっていましたが、私の方は「しんどい」が少し強い方の「たのしんどい」ですね。国語の教員ということで、経営のこと、企業のことがよくわからないので、そういった科目は正直しんどいです。ですが、そんな「わからない」私に対して、先生も同期もすごく優しく接してくださるので、なんとかついていけています。ですが、正直「なぜ私はここにいるんだろう?」と、今でも週に1度は思っていますね(笑)。
―LDCでの学びはお仕事に活きていますか?
木村さん 仕事にはいろんな形で活かされているように思います。授業で「モチベーション」について学んでは、「どうしたら先生のモチベーションを高められるだろうか?」と、「経験学習」について学んでは、「どうしたら先生たちの学びを深める内省支援ができるだろうか」と、自分の仕事に引きつけて振り返って考えています。また、仕事の進め方や、会議の進め方、研修のつくり方や評価方法など、LDC同期とのグループワークを通して学んだことも、いろいろな形で仕事に活かせているように思います。
―入学希望者に一言メッセージをお願いします。
木村さん 私も本当に教育関係者で人材開発・組織開発を学ぶ仲間、同志が欲しい、と思っています。この先、学校を幸せな場所に変えていくための鍵は人材開発、組織開発にある、と私は思っています。6期になるみなさんと共に、LDCを駆け抜けて行きたいと思っていますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。
「学校という組織を良くしたいと思っているなら、入らない理由は無くない?」
沖田さん(1年次・学校法人勤務)
―沖田さんは、学校経営に携わっているとのことですが、なぜLDCで学ぼうと思われたのですか?
沖田さん 私立高校を運営する学校法人で働いています。全国の校舎を統括する部署で学校運営全般を任されており、直近では人材の採用オンボーディング、配置などに携わっています。LDCを選んだ理由は2つあります。まず、漠然と自分自身の成長に行き詰まりを感じるようになった、というのが1つめの理由です。階層型の組織において、人材が無能化することを説明する「ピーターの法則」という概念がありますが、自分自身がまさにそうした壁に直面しているような危機感を抱いていました。今現在、管理職を任せてもらっているのですが、もっと価値を発揮できるはずだ、という感覚が常にありました。どうすればその壁を越えられるのだろうか?と考えた時、今与えてもらっている機会、経験を最大限に生かすためにも、やはりしっかりとアカデミックに学び自身の武器や自信となる知識、スキルを身につけたい、と思うようになりました。
―そもそも沖田さんが教員ではなく、学校経営に関わっていらっしゃるのはなぜですか?
沖田さん 私も英語科の教職免許を持っていて、いつかは公立高校で教員として、学校に携わりたいという思いがありました。ただそれよりも学校という組織そのものにより強い関心があり、まずは民間企業の運営ナレッジを活かした学校組織で経験を積もうと考えたのです。ところが、教育業界を見渡すと、現場の先生方の働き方の問題や、学校組織のマネジメントの機能不全を耳にする中で、こういった状況をどうにかしたい、と思うようになりました。ですが、先進的なカリキュラムや、名物授業を実施することではこういった状況を脱することはできません。結局、本丸である学校組織に目を向け、人をどうするのか、組織をどう変えるのか、というところに目を向けなければ、何も変わらないと考えています。そのことに気づき、まずは自分自身が人と組織に対してしっかりと価値を発揮できるようになりたい、と思ったのが、LDCで学ぶことを決めた2つめの理由です。
―LDCで学んでみていかがですか?
沖田さん 一番難しさを感じているのは、チーム活動です。LDCでのチーム活動の難しいところは、仕事とは違って、意思決定者としてのリーダーがいないうえ、バッググラウンドが異なる人たちが集まっているところです。大変ですが、この多様性こそが大学院の醍醐味だと感じています。あと、仕事との両立は課題ですね。仕事からの切り替えが上手くできないことがあり、バランスをとるのに苦労しています。ですが、学んだ内容はダイレクトに仕事に活きています。採用や配置、仕組みづくりなど、今までは感覚に頼って行っていたものを、きちんとした裏づけを持ったうえで行えるようになってきました。
―入学希望者に一言メッセージをお願いします。
沖田さん 学校という組織を良くしたいと思っているなら、目指さない理由は無いんじゃない?というのが入学希望者の方へのメッセ―ジです。教科の指導力や生徒対応の力をつけたいのであれば、必ずしもLDCではないかもしれません。ですが、学校という組織を良い場所にしたいのであれば、人への深い理解と組織を経営するという2つの観点を合わせ持っておく必要があります。それを学ぶ場はLDCしかない。だったら目指さない理由は無いんじゃない?とお伝えしたいです。